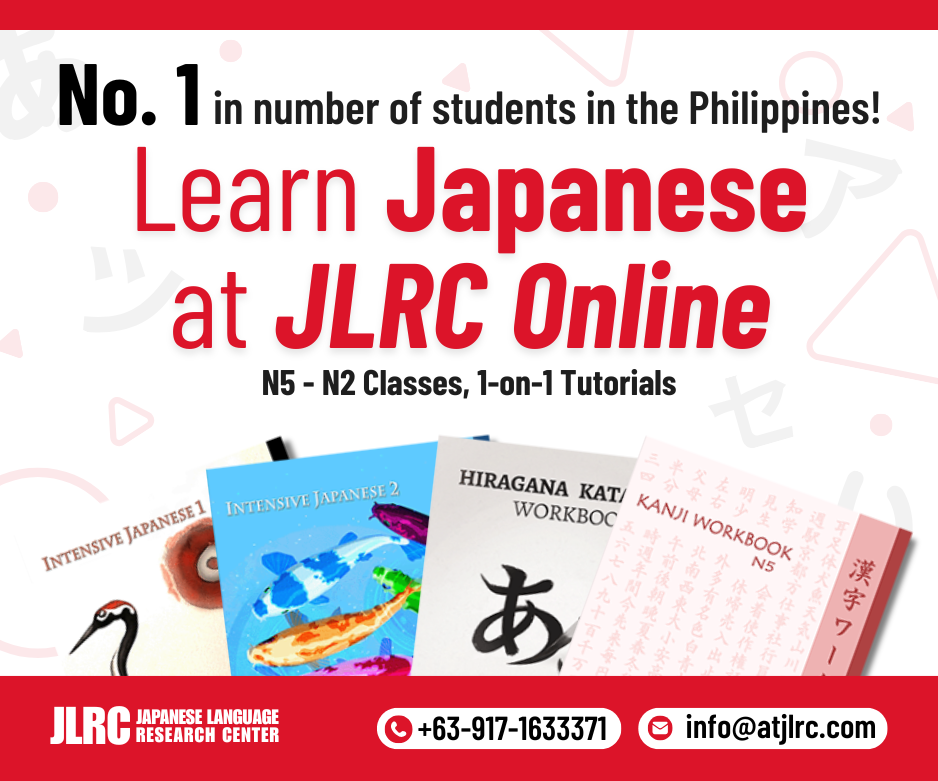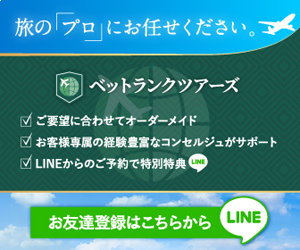深い皺(しわ)の刻まれたその手は、槌(つち)で打たれた木々の繊維をなぞるように行き来する。深く鮮やかな赤色の松皮は、水に浸けられ、漉(す)かれ、薄い一枚の紙へとその姿を変えていった。自然の中にある素材から多種多様な紙を生み出す志村朝夫の仕事は、木々や葉など、自然との「対話」そのものとして私の目に映った。
紙と対話する5日間
8月下旬、紙漉(す)きアーティスト・志村朝夫による5日間のワークショップが、ベンゲット州カパンガンにある小さな工房で開催された。この地に移り住んで30年以上となる志村は、バナナ(バショウ)科植物、パイナップルの葉脈、松の木の皮といった自然の素材を用いて多くの紙を生み出してきた。
高専で工業化学を専攻した志村は、当時静岡県富士市の製紙工場の横を流れる、公害の影響を受けて真っ赤に染まった川に衝撃を受け、和紙作りに転身を決意した。福岡県で紙漉きと藍染を学んだのち、紙漉き指導で訪れたフィリピンに、1991年より移住。現地の自然素材などに対する独自の研究を重ね、紙漉きや顔料制作をしている。

今回の素材はベンゲット松の樹皮。煮熟(しゃじゅく=繊維を煮ること)し、打開(木の棒でたたいて繊維をばらすこと)した樹皮を水に入れ、簀桁(すけた=漉き枠)を使って汲み込んで紙ができる。
5日間のワークショップでは、松の皮を用いた紙漉き、自然の顔料を使った絵画、細く裂いた紙を使った糸制作など、さまざまなことを学べる内容が揃っていた。例えば、自然顔料による絵画では、竹の炭やインディゴなどを水に溶かして顔料を作る。さらにこんにゃくパウダーを加えて独特の粘り気を持たせる。参加者たちは、その質感や色味を楽しみながら絵描きに没頭した。

工房の周辺で収集した竹の葉を燃やし、顔料などに使用する炭を作る。
また、2日目には志村とともに豊かな森林と渓流に恵まれた秘境・カンボロアン(Kamboloan)を訪れ、紙づくりに使用する自然素材に触れたり、川を泳いでその澄んだ空気と音に耳を澄ませたりした。終日工房にこもって紙と向き合うだけでなく、紙づくりを囲む環境や素材の在処(ありか)を訪ね歩くことで、様々な視点から紙について考えることができた。
自らを「紙仙人」と呼ぶ志村のもとには、人類学調査でバギオに滞在する私のほかに、マニラから2人のフィリピン人アーティストが参加した。1人は志村と同じく自然素材から紙をつくり、もう1人は紙を含む様々なテキスタイルを用いてインスタレーションを生み出す若手のアーティスト。ワークショップは志村による一方的なレクチャーではなく、紙を囲んで互いが作品のアイデアを共有したり、紙が持ちうる更なる可能性について議論したりと、とても白熱した場となった。

顔料の淡い色合いは、さまざまな素材で作られた手漉き紙に染み、滲み、2つとない作品を生む。
自然に直に触れるということ
現代の私たちにとって、自然に直接触れるという経験は少しずつ失われているのかもしれない。最後に木々の表面に触れたり、川を流れる水に手を浸したりしたのはいつだろうか。机の上のペットボトルに入った水が、一体どこから来ているのか説明できる人は多くない。私たちは少しづつ、本来近くにあるはずの自然から遠ざかっている。
志村は、紙漉きを通して自然と「対話」する。その対話には、単に紙づくりの素材としての自然の物質に限らず、その土地に刻まれた歴史や文化、人間と自然が溶け合いながら培ってきた生活の知恵も含まれている。
志村が語る話には、ベトナムや韓国における紙づくりの文化、志村の紙を使って作品を作ったアーティスト、素材が育つ環境とその質感など、ありとあらゆる知識が詰め込まれている。

漉いた紙は、工房の壁に貼り付けて1日乾燥させる。
イタリアのカリグラファー、フランチェスカ・ビアゼットンは、主著『美しい痕跡 手書きへの讃歌』の中で、「手で書く」という実践について次のように綴っている。「手で書かれたものは動いた跡であり、手が筆記具を介して媒体に痕跡を残す」。ビアゼットンの言う「跡」という表現は、志村がその手や身体、そして道具を通して自然に向き合い、素材の変化に絶え間なく関与する営みをよく表しているように思う。
5日間のワークショップは、志村が作り上げてきた紙づくりの痕跡を辿りながら、彼がこの先歩んでいく新たな紙づくりの未来について思考を巡らせる時間でもあった。
青い月の日に
来年の8月31日、「青い月の日(Blue Moon day)」と呼ばれるその日に、志村は再びワークショップを執り行うと言う。私を含む3人の参加者たちは、来るべき再会の日を楽しみに、それぞれの活動に戻っていった。
Photo by 牛丸維人
オーフス大学(デンマーク)映像人類学修士課程在学。ベンゲット地域の視覚障害者を取り巻くケアの実践とエコロジーに関する人類学的調査のため、2022年4月よりバギオに滞在。フォトグラファーとしても活動中。 https://masatoushimaru.com/
志村 朝夫 ウェブサイト(Facebook) https://www.facebook.com/asao.shimura.7
志村朝夫のオンラインワークショップ (2022年10月8日&15日)