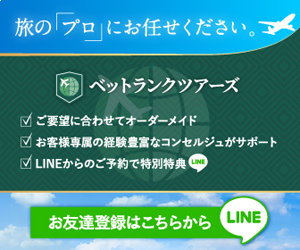フィリピンの貧困地区のごみ集積場で労働に従事する子どもたちを8年の歳月をかけて撮ったドキュメンタリー映画『YIELD』。2018年フィリピン映画芸術科学アカデミー(FAMAS)賞で最優秀ドキュメンタリー賞をはじめ、数々の賞に輝いた同作の最終編『子どもの瞳をみつめて』(原題:YIELD Final Version)が、4月 29日から東京・新宿K’sシネマを皮切りに、日本各地で上映されることになった。同作品に込めた思いを、瓜生敏彦監督に聞いた。
瓜生敏彦(うりう としひこ)
1958年千葉県三里塚生まれ。実家が成田空港建設に反対する三里塚闘争の拠点となったことからドキュメンタリー映画に関心を持つ。『東京裁判』(1983年 監督:小林正樹)、『神田川淫乱戦争』(1983年 監督:黒沢清 )、『ドレミファ娘の血は騒ぐ』(1985年監督:黒沢清)、『ゴンドラ』(1987年 監督:伊藤智生)など多数の映画、テレビ作品の撮影に携わる。1995年、NHKドキュメンタリー「フィリピン、スモーキーマウンテンが消える日」を撮影中、フィリピンの警察から腹部に銃撃を受け、重傷を負う。奇跡的に回復した後、貧困地域のパヤタスとスモーキーマウンテンに暮す子どもたちをテーマにした四ノ宮浩監督によるドキュメンタリー映画『忘れられた子供たち/ スカベンジャー』(1995年)、『神の子たち』(2001年)、『BASURA バスーラ』(2009年)の撮影に参加。2001年にはパヤタスとスモーキーマウンテンの子どもたちの「学校で勉強したい」という希望をかなえるため、無料の学校を設立した。同校は現在までに約5000人以上の卒業生を輩出している。さらに子どもたちの歌やダンス、演技などの才能を伸ばし、発揮する場としてNPO法人クリエイティブ・イメージ・ファウンデーション ( Creative Image Foundation )とTosh Entertainmentを設立し、子どもたちの支援を行っている。
映画ジャンルの先入観なく
『子どもの瞳をみつめて』は、3月に行われた大阪アジアン映画祭の特別招待作品として上映されました。観客の反響を聞いて思ったのは、私が伝えたいことが狙い通り、伝わったということ。ドキュメンタリーは社会問題を追及する内容でなくてはならない、といった先入観にとらわれることなく受け入れてもらえたことをうれしく思います。
2018年に『YIELD』を公開した時、日本の映画関係者に見せたところ私の意図が伝わらないことがありました。その一方、フィリピンでの映画祭で劇映画とともに10本の作品に選ばれてノミネートされたことがあります。後から知ったのですが、ドキュメンタリーを選ぶことには反対意見もあったそうです。しかし、審査員が「この映画にはパワーがある」と認めてくれて、劇映画と一緒に選ばれたと知りました。それを聞いてフィリピンの審査員の見識に感銘を受けましたね。
生き方を問い直すきっかけに
私は、20歳の頃から文字、言葉では伝えることができないことを映像で伝えたいと思ってきました。『子どもの瞳をみつめて』にもナレーションは入りません。同作は『YIELD』をフィリピン国外での上映を想定して編集しました。プロの俳優ではない、普通の子どもを起用して撮ったドキュメンタリーのような劇映画といえるかもしれません。ただ、劇映画の撮影はある意味設計図に沿ってつくられていくのに対し、ドキュメンタリーは撮影中に何が起きるかわからない。ジャズのように即興で対応して撮影した作品です。
この作品を見て、日本の人には、「幸福とは何か」「生きる価値とは何か」「家族の絆とは何か」と、これまでの生き方を問い直して、考えてほしい。私が敬愛するソ連の映像作家アンドレイ・タルコフスキーを見た後のように、あたかも哲学書を読んだ後のように感じてもらえたら。そして、100人が見たら、100人が違う感想を持ってもらっていいと思います。